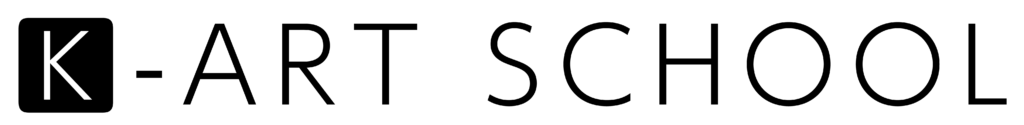こんにちは、いけべけいこです。
子どもが描いた絵やつくった作品を見て、「この子らしいな」と感じたことはありませんか?表現には、その子だけの視点や気持ちがにじみ出ています。しかし、忙しい日常の中で、子どもたちの小さな個性の芽に気づくことが難しい場面も少なくありません。個性を育むには、ただ自由にさせるだけではなく、しっかりと受け止めてあげる姿勢が必要です。
表現活動の中で自然に現れる子どもの個性に焦点を当てながら、どうすればその個性を大切にできるのか、家庭や教育の場で取り入れられる関わり方や考え方をご紹介します。子どもたちがのびのびと自分らしさを表現できるよう、日々の関わりのヒントを一緒に探していきましょう。
目次
子どもの個性を理解するとはどういうことか
一人ひとりの子どもが持つ「個性」は、目に見える特徴だけではありません。話し方や行動、感じ方や考え方など、その子がその子らしくあるためのすべてが個性です。大人の目線だけで良し悪しを決めず、まずはその子の中にある思いや背景を尊重することが、個性を理解する第一歩となります。
「個性」とは何かを改めて考える
多くの場合、「明るい子」「人見知りな子」といった言葉で子どもを表現しがちですが、それはごく一部の側面にすぎません。個性とは、その子だけが持っている感受性や興味関心、反応の仕方などを含めた全体のことを指します。周囲の期待に応えようとするうちに、本来の個性が見えにくくなることもあります。
周囲との違いを受け入れる大切さ
他の子と比べて「うちの子は変わっている」と感じたときこそ、大切なのは否定ではなく理解です。違いがあるからこそ、多様な考えや感じ方が育まれます。個性を尊重するとは、他と同じでなくてもいいと認めることであり、その違いにこそ価値があると考えることです。
良し悪しで判断しない関わり方
子どもの行動や発言に対して、「それは正しい」「それは間違っている」とすぐに評価してしまうと、子どもは自分の感じたことを口に出しづらくなります。個性は「直すべきもの」ではなく、「育てるもの」として関わる必要があります。まずは、子どもの気持ちや表現をありのままに受け止めることから始めましょう。
個性は変化しながら育つもの
個性は固定されたものではありません。成長とともに変化し、環境や経験によって磨かれていくものです。そのため、今の姿だけを見て判断するのではなく、時間をかけて見守る姿勢が大切です。表現活動のように、自由に発想できる場があることで、子ども自身が新たな自分に気づき、個性がさらに育っていきます。
子どもの表現にはすべて意味がある
子どもが描く絵やつくる作品、ちょっとした言葉やしぐさには、必ず何かしらの意味が込められています。大人には何気ないように見えても、子どもにとってはその時々の感情や考えを外に出すための、大切な手段です。その一つひとつに耳を傾けることで、子どもの心に寄り添った関わりができるようになります。
作品に表れる子どもの気持ち
色使いや形、構図の選び方など、表現にはその時の気持ちが反映されます。たとえば、同じテーマでも明るい色を使う子もいれば、落ち着いた色を好む子もいます。それは感情の現れであり、無意識のうちに自分の内面を表していることもあります。完成した作品だけで判断するのではなく、どんなふうに取り組んでいたかを見守ることが大切です。
話さなくても伝わる思い
言葉にするのが難しいとき、子どもは表現を通じて気持ちを伝えようとします。何を描いたのか説明できなくても、そこには思いや考えが込められています。大人が無理に意味を求めるのではなく、「この色を選んだのはなぜかな?」「この形、面白いね」と関心を持って関わることで、子どもは安心して自分を出せるようになります。
自由な表現が自己理解を深める
自分の気持ちや考えを表に出すことで、子ども自身も「自分はこう感じていたんだ」と気づくことがあります。特に、アートや造形などの活動は、言葉だけでは整理しきれない感情を形にできる貴重な時間です。こうした表現の積み重ねが、自己理解や自己信頼へとつながっていきます。
感情を安心して出せる環境の重要性
表現するには、「何をしても大丈夫」と思える安心感が必要です。否定される心配があると、子どもは本音を出しにくくなります。だからこそ、大人が「どんな表現でも受け止めるよ」という姿勢で関わることが、心を開く第一歩になります。そうした信頼関係の中でこそ、個性豊かな表現が育まれていきます。
家庭でできる個性を尊重する関わり方
子どもが最も安心して自分らしさを出せる場所、それは家庭です。日々の生活の中で個性を大切にする関わりを積み重ねることで、子どもは自分に自信を持ち、のびのびと成長していきます。特別なことをする必要はありません。ほんの少しの心がけで、子どもの個性はより豊かに育っていきます。
否定しないで聞く習慣を持つ
子どもが何かを話し始めたとき、すぐに「それは違うんじゃない?」と反応していませんか?意見や発想を否定せず、まずは「そうなんだね」と受け止める姿勢が、子どもの自己表現を支えます。大人の正しさよりも、子どもの気持ちに寄り添うことが、信頼関係を築く鍵になります。
決まった「型」に当てはめない
「男の子はこうあるべき」「女の子はこうするもの」といった枠に当てはめると、子どもは本来の個性を表に出しにくくなります。好きな色や遊び、興味のあることは一人ひとり違って当然です。大人が柔軟に受け入れることで、子どもは安心して自分らしくいられるようになります。
結果ではなく努力を認める
「うまくできたね」と成果を褒めることも大切ですが、それ以上に「がんばってたね」「工夫してたね」と過程を見てあげることが、子どもにとって大きな励みになります。努力を認められる経験が、「自分のやり方で大丈夫なんだ」という自信につながっていきます。
親も一緒に楽しむ姿勢を持つ
何かを一緒に作ったり遊んだりするとき、親が楽しそうにしている姿を見せることで、子どもも安心して取り組めます。「上手にやらなきゃ」と構えずに、「一緒にやってみようか」と声をかけるだけで、自然と会話や笑顔が生まれます。その時間が、子どもの心をゆるめ、個性を伸ばす土壌になります。
表現活動が子どもの自信を育てる理由
子どもにとって「自分の思いを形にする」ことは、単なる遊びではなく、自分自身を知り、信じるための大切な体験です。表現活動の中で得られる達成感や承認は、子どもの心に強く残り、自信となって日々の行動にも影響を与えます。作品を完成させるまでの流れの中には、多くの小さな成功と挑戦が詰まっています。
成功体験が生まれる仕組み
K-ART SCHOOLでは難しいプログラムがたくさんあります。最初は「できないかも…」と思っていたことでも、しっかりとしたプログラムにより、最後まで取り組むことで「自分にもできた!」という実感が生まれます。その体験が自信となり、次の挑戦への意欲につながります。完成という明確なゴールがあり、そこに向けて努力する過程そのものが、子どもの成長を後押しします。
自分の考えに価値があると感じる瞬間
「その発想、おもしろいね」「この色づかい、すてきだね」など、大人からのさりげない言葉が、子どもにとっては「自分の考えって認められるんだ」という実感になります。評価ではなく共感があることで、子どもは自分の感じたことや考えたことを肯定的に受け止めるようになります。
自己肯定感と創造力の関係
自分に価値があると感じることは、創造力の土台になります。「自分のやり方でいいんだ」と思えると、自由に発想することができ、新しい挑戦にも前向きになります。自己肯定感が高まると、表現に対する抵抗感がなくなり、自分らしさをのびのびと出せるようになります。
自由と安心のバランスが鍵
ただ「自由にやっていいよ」と言われるだけでは、かえって不安になる子もいます。K-ART SCHOOLでは一定の枠の中で安心して自由に表現できる仕組みになっています。見守ってくれる講師や、方向性がしっかりしているので、その中で自分の判断や工夫が尊重されると、子どもは「自分で選んでいいんだ」と感じ、自信を持って表現できるようになります。
多様な関わりの中で育まれる個性
子どもは自分一人の力だけで成長するのではなく、周囲との関わりの中で少しずつ変化し、個性を育てていきます。家庭だけでなく、学校や教室、友達とのやり取りなど、さまざまな場面での経験が重なり合うことで、「自分らしさ」がかたちづくられていきます。他者との関係性の中で気づくことは、子どもの成長に欠かせない大切な要素です。
友達との違いを学ぶ大切な経験
友達と一緒に活動する中で、「あの子はこうするけど、自分はこうしたい」という違いに気づくことがあります。その違いが否定されず受け入れられると、子どもは「自分の考えも大事なんだ」と感じられるようになります。相手との違いを認めながら自分を理解する経験は、個性をはぐくむ土壌となります。
集団の中でこそ発見できること
一人では気づけなかった自分の得意や苦手も、集団の中での活動を通じて見えてきます。「〇〇ちゃんは発想が豊か」「自分は最後までやり抜くのが得意」といった気づきが、子ども自身の自己理解を深めます。他者との関わりは、自分の存在を再確認する機会にもなります。
他者を認める力が自分も育てる
誰かの作品を見て「すごいね」と思ったり、「こんな考え方もあるんだ」と感じることは、自分の価値観を広げるきっかけになります。他者の良さに気づくことで、自分の良さにも目を向けられるようになり、自然と自己肯定感も育まれていきます。
比較よりも観察を大切に
「誰が一番上手か」「早くできたか」といった比較は、子どもの創造力を萎縮させる原因になることがあります。それよりも、「この子はどうやって作ったのかな」「どこに工夫したのかな」と観察する視点を持つことが、個性を理解し合う第一歩になります。大人もその姿勢を意識することで、子どもたちは安心して表現できるようになります。
K-ART SCHOOLが大切にしている個性の育て方
子どもの「らしさ」を育てるには、安心して表現できる環境が必要です。絵の上手さや正解だけを求めるのではなく、その子だけが持つ視点や感性に光を当てることで、自分らしくいられる土台がつくられていきます。無理に引き出すのではなく、自然と表に出てくる個性を見つけてあげて、褒めて伸ばすことを大切にしています。
「上手さ」より「自分らしさ」を認める
技術的な完成度ではなく、その子の内面がにじみ出た表現を大切にしています。「これは面白いね」「この色の組み合わせに気づいたんだ」といった声かけは、子ども自身の発想に価値があると伝えることになり、表現への自信を育てるきっかけになります。
作品づくりの過程にこそ価値がある
完成された作品だけを見て評価するのではなく、つくっている途中の時間こそが創造の源と考えています。「なぜこの形にしたのか」「どうしてそのアイデアを選んだのか」など、思考や試行錯誤の痕跡が、子どもの個性を最もよく表します。その過程を一緒に感じ取ることが、深い理解につながります。
自己肯定感を育む三つの視点
個性を育てるには、心の安定が欠かせません。「自分は必要とされている」「がんばった分だけ認められる」「自分を好きでいられる」という3つの実感があることで、のびのびと表現できるようになります。それぞれの子が持つ強みを見つけ、丁寧に関わることが、自然と心の成長を促します。
表現を通じた心の変化を見守る
ことばでは伝えにくい気持ちも、作品にすることで表に出ることがあります。そうした変化を無理に解釈しようとせず、子ども自身が「自分ってこうなんだ」と気づけるように支える姿勢が大切です。関わる大人は、答えを教えるのではなく、気づきを引き出す伴走者であることが求められます。
まとめ
子どもの個性は、誰かと比べるものではなく、その子自身の中にある「違い」として尊重されるべきものです。表現することを通じて、子どもは自分の気持ちや考えに気づき、それを人と共有する力を育んでいきます。日々の中で少しずつ積み重ねていくその経験が、子どもたちの自信となり、自己肯定感の土台をつくっていくのです。
大人の役割は、子どもが安心して自分を出せるような空間を整え、言葉や表現を否定せずに受け止めることです。その子らしさや取り組みの姿勢にも目を向けることで、子どもたちは「認められている」という実感を持つようになります。
K-ART SCHOOLの完成度の高い作品を完成して持ち帰る事によって、ご家庭でもどのように工夫したのか、頑張ったのかを説明し、質問されるさらに自分の自信となります。
K-ART SCHOOLでは、しっかりとしたプログラムの中で、子ども一人ひとりの個性が自然と育まれるようなレッスンを心がけています。一定の枠の中で、安心して自由な発想をし、子どもたちは楽しく自分らしさを見つけていきます。